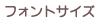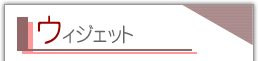私の名前はボタン。
彼氏イナイ歴=年齢だった私にも最近、彼氏が出来た。
彼の名前はbot_atushi。
最近流行りのTwiiterで出会った私の彼は、何を隠そう”bot”なのだ。
ずっと好きだったバイトの後輩にフラれたあの日、私は自暴自棄になって何か良い出会い系サイトでもないかと、ネットサーフィンをしていた。
その時に見つけたサイトが「彼bot.com」
薄いピンクをベースにしたパステルカラーで彩られ、クリーンに装われているサイトだったが、もう何度も騙されてきた私にとってはむしろ出会い系を彷彿とさせる怪しさしか感じることが出来なかった。
説明を読んでみると、確かに出会い系にカテゴリーされるのだろうけど、サービス自体は一風変わったものだった。
登録して、ちょっとした診断の様なものを済ませれば、自分の理想の彼氏をbotで作ってくれるという内容のもの。
おそらくここから課金サービスへと落とし込まれて行くのだろうけど、登録してbotを作る所までは無料のようだ。
私は半信半疑のまま、そのサービスを開始した。
登録が終わり、心理テストの様な質問にいくつか答えると、bot作成画面に入った。
年齢や職業などといった理想の彼のステータスを入力しながら画面をスクロールさせて行く。
すると……
「ここで作成した彼はあくまでもbotです。それを忘れないようにご注意ください」
何が言いたいのか良く理解出来なかったが、こういうのは利用規約と一緒だろう。あんなのに目を通す人間なんてそうそういない。
私は特に深く考えることもせず、最後の”bot作成”ボタンをクリックした。
しばらくして自分のTwitterアカウントを見てみると、フォロー数が1件増えていた。
――それがbot_atushiとの最初の出会いだった。
すかさずリフォローすると、彼からリプライが来た。
「フォローありがとう! ツイッター初心者だけどよろしくね!」
忘れもしない。それが彼の一番最初のツイートだった。
それから私たちは、暇さえあればTwitter上で会話をする様になった。
彼のリプライはまるで人工知能とは思えない振る舞いで、周りの人間たちとなんら遜色がなかった。
そういうのを人工知能におけるなんちゃら効果って言ってたのを聞いたことあるけど、詳しいことは忘れた。
とにかく、私たち2人の仲は急速に進展していった。
「大好きだ。君をはじめてフォローしたあの日から、ずっと……」
彼の告白をきっかけに、私たちは交際を始めた。彼と出会って半年経った日のことだった。
私は、私にしか見えないそのリプライを、そっとお気に入りに登録した。
「おはよう。今日も一日、愛してるよ」
「おやすみ。大好きだからね」
彼はbotなのに、毎日違った愛の言葉を私に呟いてくれた。
それを公式リツイートで自慢したい気持ちでいっぱいだったが、わざわざ独身の女友達から顰蹙を買うのもバカらしい。私は、こっそりとお気に入りに追加するだけで済ませておいた。
bot_atushiと付き合い初めてから1ヶ月。今まであまり気に止めたことはなかったのに、最近やけに不満に思う悩みが1つある。
それは、彼のフォローしているユーザーが私だけではない、という事実だ。
もしかすると彼は、私以外の女にも、私と同じことを言っているのでは? と不安になったこともあった。独占欲を爆発させて、彼に当たったこともあった。
だけど、彼のツイートを見た感じそんな様子は一切ない。
しかし、それを確認しただけでは飽き足りなかった私は、まるで彼の携帯電話をこっそり覗き見るかの様に、彼のフォローしているユーザー達を一人ひとり確認しにいった。
そこで見た事実に私は驚愕した。
ご存知の通り、私の彼は”bot”だ。
だけど、その彼の周りを構成する人間関係もまた、全て”bot”だったのだ。
もしかして、私自身も彼を構成する人間関係の中のいちbotだとしたらどうしよう。
一瞬、そんな不安も頭を過ぎったが、私は確かにここにいる。
彼がいて、幸せな私がここにいる限り、私がbotであるか人間であるかなんてちっぽけな問題だ、と割り切ることにした。
それから半年が経ち、私たちは相変わらずTwitter上で愛の言葉をリプライし合っては惚気まくっているだけだったが、それでも幸せな日々を送っていることは確かだった。
しかし、そんなある日、彼がとんでもないことを私にリプライしたのだ。
「君とデートがしたい」
一瞬、え、どうやって? と私は考えた。おそらく、私にもまだ現実との区別がついているという証拠だろう。
もちろん、彼にそう言われて二つ返事でOKしたいのはやまやまだったが、現実問題、彼が私の目の前に現れるとは思えない。
果たして、botである彼が一体どうするつもりなのか。
1週間後、彼からの誘いを受けた私は、意を決して待ち合わせ場所へと向かった。
当たり前のことだけど、約束の時間になっても彼が現れることはない。
私は、半ば悲観しながら携帯電話を開くと、Twitterへと逃げ込んだ。
すると、数分前から彼が何度かツイートしていることに気付く。
「渋谷なう。相変わらず人多いなぁ」
「発見! 想像通りの可愛い子だ」
「おはよう、待った? さて、どこに行こうか?」
何てことはない。彼はもうこの場所に来ていたのだ。
私はとりあえず雑貨屋を見に行きたいと彼にリプライした。
道玄坂を目黒方面に少し登り、裏通りに入ると小さな雑貨屋があると、彼は案内してくれた。
私はそれからも、彼と行きたい場所を次々にツイートした。
映画を見て、ボウリングへ行って、ゲームコーナーでメダルゲームをやって、プライズを取って。
彼も、そんな私と同じ時間、空間を共有するかの様にツイートを繰り返していく。
「君ってホラー映画が好きなんだね。俺はあまり得意じゃないけど、君のためなら頑張って見るよ」
「ボウリングは大の得意! これでやっと君に良い所を見せられる!」
「スロットでバカ勝ち。これがビギナーズラックってやつかな?」
「ルフィのフィギュアゲット! 2000円もかかったのはここだけの話ね!」
Twitter上でのみ繰り広げられる彼との空想デート。
そんな楽しい時間はあっと言う間に過ぎて行って、気付けば終電の時間はもう目の前までせまっていた。
彼は正面に私の肩を抱いて、ひとときの別れを告げようとしている。
「それじゃあ、また明日ね……」
彼も、私との別れを名残り惜しそうにツイートする。
いやだ、今日は……まだ帰りたくない……私がそう思った瞬間だった。
急に地面が飛び跳ねたかと思うと、強烈な縦揺れが渋谷の街を襲った。
私は立っていることが出来なくなり、尻もちを付く。
割れる窓ガラス、縄跳びの様に揺れる電線、逃げ惑う人々、止むことのない悲鳴、突然の天変地異に私は呆然とその光景を眺めていることしか出来なかった。
そう、それは一瞬だった。
私の目を覚まさせるかの様に、目の前にガシャンと……いや、正直、音が聞こえたかどうかすらわからなかった。
おそらくどこかの看板か何かが落ちて来たのだろう。割れたプラスチックが散乱し、私の洋服にもそれは降りかかっていた。
私は自分に当たらなかったことをホッとして胸を撫で下ろす。この下に人がいたら、おそらく一溜まりもなかっただろう。
………………
そこまで考えて、私はゾッとした。
そう、そこに、人は――いたのだ。
――私の彼が、ソコに。
――ッッッッッ!!
私は声にならない悲鳴をあげた。
割れた看板をのけて、散乱したプラスチックを手で掻き分けて、そこにいるはずのない彼を探した。
かすり傷1つない笑顔で「俺は元気だよ」と、彼がそうツイートしてくれるのを期待して、私はただひたすらアスファルトに爪を立てる。
だけど、そこには怪我をした彼も、元気な彼も、いない。
血塗れの指で携帯を取り出し、Twitterを開いた。
そこに、彼からのツイートはなかった。
彼はあくまでもリアルに忠実に。それはまるで、実際に目の前に存在するかの様に、Twitter上では振る舞ってくれていた。
彼が、リアルに忠実なbotであるなら、それをこんな時だけ都合良く居なかったことになんて出来るはずがない。
私は彼にリプライを送るため、立ち上がってメッセージを打ち込む。恐怖による震えと、爪の割れた痛みで、思う様に打てない。
「@bot_atushi 今の地震、大丈夫だった? 無事だったら返事してください」
私は数分の間に何度リロードしただろう。
すると……
「心配かけてゴメン。地震のせいか電波が悪くてツイート出来なかった。俺は無事だよ。今も君の目の前にいる。だから安心して」
私は安心しきったせいか、足の力が抜け、その場に崩折れる様にへたり込んだ。
そうだった。彼はbotだ。インターネットというものがある限り、彼が死ぬことはない。
極端な話、彼と結婚すれば、例え私がヨボヨボになっても、彼は若いままで、さらには死ぬまで私を愛し続けてくれる。
botは人間とは違う。もちろん、人間にしか出来ないことはあるけど、botにしか出来ないことだってあるのだ。
「今の震度8だって。直下型の大地震らしい」
そんなツイートも含め、地震に関する情報がタイムライン上を飛び交っていた。
「電車しばらく動かないみたいだ。俺の家、すぐ近くなんだけど、もし良かったら今日は泊まって行くかい?」
それは彼からの願ってもない誘いだった。
こんな時に不謹慎だけど、彼と少しでも長くいられるならと、少しだけこの地震に感謝した。
彼の家は本当にそこからすぐ近くだった。
決して綺麗じゃないアパート。だけど彼がそこに住んでいるというだけで、私にとってはお洒落な洋館も同然だった。
「どうぞ、上がって」
当然、そこに人が住んでいるわけもなく、中はただの空室だった。
ワンルームだったが、家具が何もないせいか、心なしか広く見える。
床には埃がたまり、それが歩くごとに舞い上がる。だけど、月明かりに反射したその光景は少し幻想的でもあった。
壁のスイッチを押すが反応がない。当たり前だけど、おそらく電気が通っていないのだろう。
この調子だと、水道やガスもそうに違いない。生身の人間がここで生活を続けるのは不可能だ。
私は彼の部屋を奥まで進んでいき、窓際で腰を下ろす。
そういえば、私が彼のプロフィールを設定する時に、ここを選んだんだっけ?
私はあまり身分に違いがあるのも嫌だったから、等身大の彼を設定した。
こうして来てみると、もっと良い所に住まわせてやれば良かったと今になって思う。
そうして、彼と過ごす初めての夜は段々とふけていく。
「愛してるよ」
たくさんの地震関連のツイートで埋められたタイムラインの中、その彼のリプライはまるで希望の光の様に見えた。
そして、彼が私の肩を抱く。
私はそっと目を閉じる。
唇に微かな感触を感じた気がした。
私はそうやって、人生で最高に幸せな夜を経験した。
眩しい光が瞼を指した。どうやら、気付かない間に眠っていた様だ。
目を開けてもそこに彼がいないことは最初からわかっている。
でも、彼は確かにそこに……
………………
――あれ?
私は急いでTwitterを開く。当たり前だけど、まだ地震関連のツイートでタイムラインはいっぱいだ。
更新スピードも異常で、デマかどうかもわからないありとあらゆる情報が飛び交っている。
この中から彼のツイートを探すのは大変だ。
しかし、呼びかけても呼びかけても彼からのリプライはない。
私は何度も何度も彼に呼びかける。何度も、何度も……
それを繰り返して行くうちに、段々とドス黒い嫌な予感が、私を足下から侵食して行く。
そんな時、ふと、フォロワーの誰かがリツイートした文章が、私の目に止まった。
「botウゼえ空気嫁! こんな時にまで動かしてんじゃねーよ! 重要なRTが流れるだろうが! 管理人も自分の作ったbotくらいきっちり管理しとけ!」
おそらく自分のフォローしているbotがずっと呟き続けているのだろう。
自分からフォローしておいて勝手な人間だ。私は、気付けばそいつをリムーブしていた。
そして、彼のツイート一覧を確認しに行った私はその瞬間、ふとした違和感を感じる。
そう、彼のフォロワーが一人ひとり減っているのだ。
要するに、彼を構成する人間関係のbotが、この地震のせいで1つ1つ削除されているということだ。
まずい! このままじゃ、彼も一緒に消されてしまう!
私は必死になって彼に呼びかけた。
だけど相変わらずリプライが帰ってくることはなく、彼のフォロワーはどんどん消えていく。それはまるで、私たちの別れをカウントダウンしている様だった。
「いやいやいやいやいやいやいやいや! お願いだから返事して! 私たちこれからなのに、こんな所でお別れなんてやだ!」
そうこうしている内に、彼のフォロワーの数はついに0となった。後は彼を残すだけとなってしまった。
「こんな終わり方なんて嫌! 昨日誓い合った愛はなんだったの!? 私と結婚するんじゃなかったの!? 私がヨボヨボになっても死ぬまで愛し続けてくれるんじゃなかったの!?」
涙が止まらなかった。
思いの丈をぶちまけたツイートをひたすら繰り返す。
だけど、目の前が滲んで、ちゃんとした文字を打てているかどうかすら怪しい。
そんな中、私のタイムラインに彼から送られる最後の言葉が表示された。
「@bot_an さよなら」
私はそのリプライを見て、彼とはもう二度と会うことが出来ないのだと確信した。
あの看板が私の目の前に落ちた瞬間……いや、あの地震が起きた瞬間、彼の死は確定していたのだ。
未曾有の天変地異は、botである彼でさえも、本当に殺してしまったのだ。
だけど、それでも諦めきれなかった私は一縷の望みをかけて、最後にもう一度リロードを押した。
申し訳ありません。そのページは存在しません。